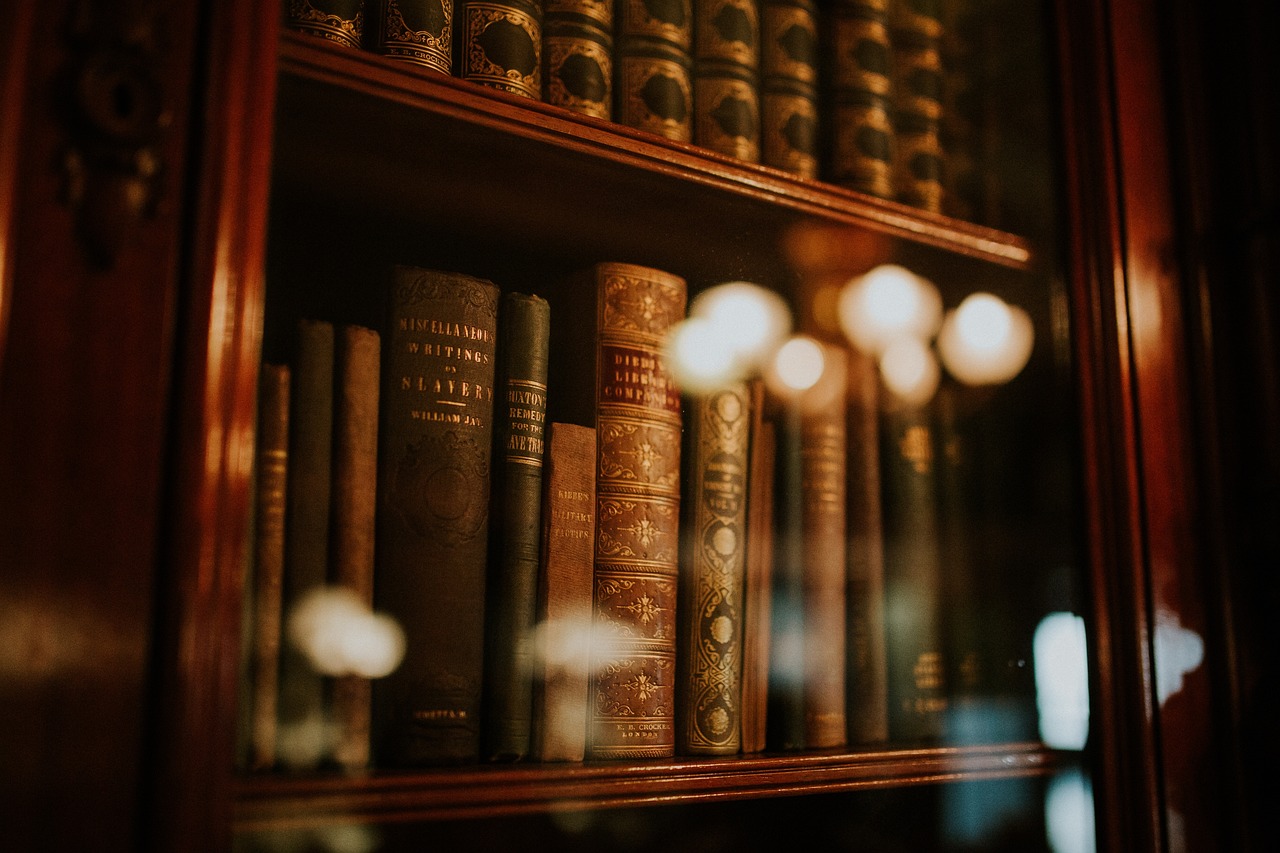「もし、夫に先立たれたら…私はどうすればいいのかしら」「財産の管理って、元気なうちに何を準備しておけばいいの?」
60代、70代のご夫婦、特にお子さんがいない場合、老後や相続に対する不安は決して他人事ではありません。
いざという時に慌てずにすむよう、備えておくべき制度はいくつかあります。
この記事では、老後や相続への備えとして代表的な3つの制度――遺言、後見制度、家族信託について、その違いと使い分け方を行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1 まず押さえておきたい、3つの制度の役割の違い
結論から言うと、以下のように「何に備えたいか」で、選ぶ制度が異なります。
・遺言:亡くなった後に、財産を「誰にどう分けるか」を決めておくもの。
・後見制度:認知症などで判断能力が亡くなった時、誰が手続きを代行するかを決める制度
・家族信託:将来に備えて、元気なうちに財産の使い道や管理を任せておく契約
それぞれ性質が異なり、併用も可能です。では、ひとつずつ見ていきましょう。
2 遺言書―「自分が亡くなった後」のために
要点と結論
亡くなった後の「財産の行き先」を自分の意志で決めておきたいなら、遺言書が必須です。
定義
遺言書とは、本人が死亡したときに備えて「誰に、どの財産を、どのように渡すか」を明記した書類です。民法で内容や形式が決められています。
基準
中でも公正証書遺言が最も確実で安全。公証役場で公証人と証人2人が立会い、法的ミスがないように作成されます。
事例
例えば、ご主人が亡くなり、奥様にすべての財産を残したい場合。子どもがいなければ、ご主人の兄弟にも相続権がありますが、「全財産を妻に相続させる」と遺言で記しておけば、兄弟の取り分はゼロにできます(※兄弟姉妹には遺留分がないため)。
3 後見制度―「判断できなくなったとき」のために
要点と結論
認知症などで判断力を失ったときの手続き、財産管理に備えるなら、後見制度を検討しましょう。
定義
後見制度には2種類あります。
・法定後見:すでに判断能力が低下した時に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度
・任意後見:元気なうちに「この人に任せたい」と契約しておく制度
基準
柔軟性を求めるなら「任意後見」。元気なうちに契約でき、希望の内容で管理してもらうことができます。
「法定後見」は、裁判所が関与するため、制限が多くなります。
事例
例えば、ご主人が認知症になった後、奥様が銀行口座からお金を引き出せず、施設の費用が払えなくなる…ということもあります。
任意後見契約があれば、事前にこうした管理を家族に任せられます。
4 家族信託―「将来の柔軟な財産管理」のために
要点と結論
将来に向けて、財産を家族に託しながら、本人の生活費や介護費用を管理してもらいたいなら、家族信託が選択肢になります。
定義
家族信託とは、「信頼できる家族に財産の管理、処分を託す契約」です。
契約に基づき、財産の使い道や分け方まであらかじめ決めておくことができます。
基準
信託の対象になるのは、不動産、預貯金、株式など。後見制度と違って、裁判所の関与がない分、柔軟で実践的な管理が可能です。
事例
例えば、ご主人が将来認知症になった場合、奥様が生活費のためにご主人名義の不動産を売却しようとしても、後見制度下では裁判所の許可が必要になります。
一方、信託契約をしておけば、あらかじめ決めた家族がスムーズに不動産を売却し、必要な費用に充てることができます。
5 それぞれの制度の違いと組み合わせ方
以下のように使い分けると効果的です。
| 制度 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 遺言書 | 死後の財産の分け方を指定 | 自分の意思を法律的に残せる |
| 任意後見制度 | 判断力低下後の管理を準備 | 元気なうちに信頼できる人を指名可能 |
| 家族信託 | 財産の柔軟な管理・処分 | 自宅の売却や活用にも対応できる |
組み合わせも可能です。
例えば、遺言書で死後の財産分配を決め、任意後見で生活管理を託し、家族信託で不動産の柔軟な管理を任せる――
こうした多重の備えが、老後とその後を支える「安心」につながります。
6 制度を「知っておくだけ」で選択肢が増える
子供のいないご夫婦にとって、財産をどう残すか、老後をどう過ごすかは非常に大きなテーマです。
ただ、「制度が難しそう」「今は元気だから大丈夫」と先延ばしにしてしまう方が多いのも事実。
でも、元気なうちだからこそ、準備ができるのです。
行政書士として、私は「遺言」「任意後見契約」「信託契約」の作成を支援を通じて、ご夫婦が安心して老後を迎えられるようお手伝いしています。
気になる制度が一つでもあれば、まずはお気軽にご相談ください。些細な疑問からで大丈夫です。
↓