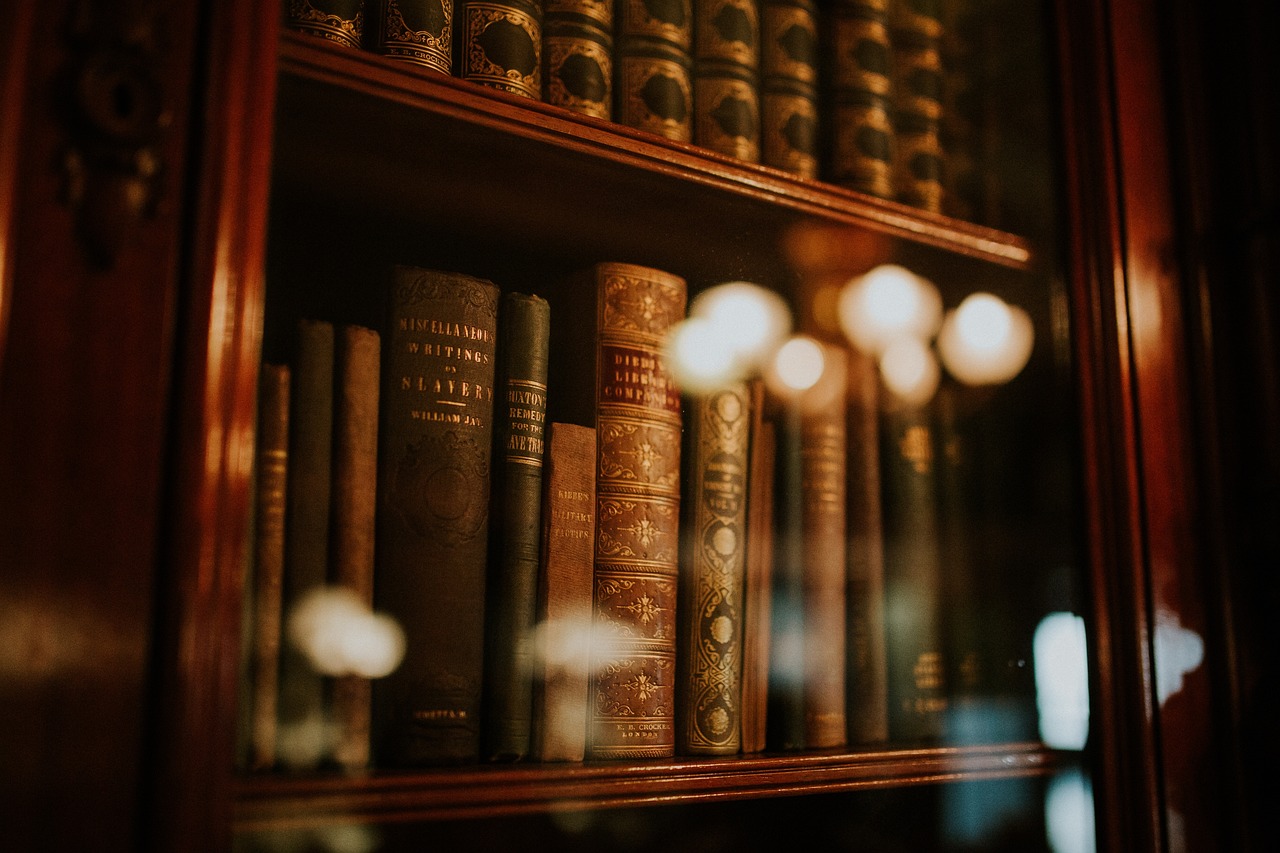「実家は親が住んでいるから空き家の話なんて関係ない」
そう思っていませんか?
ですが近年、親が介護施設に入ったことをきっかけに「実家が空き家になった」というケースが増えています。
その背景には「2025年問題」や「認知症による契約の壁」といった複雑な事情があり、家族にとっては想像以上に切実な問題です。
今回は、将来「空き家にしないため」に今から知っておきたい準備について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1 実家が空き家になるきっかけは、親の介護施設入所
2025年には、団塊の世代がすべて75歳以上になります。
それに伴って増えるとみられているのが「空き家」です。
多くの空き家のきっかけは、親が施設へ入所すること。
一度入所すると、自宅へ戻る可能性は低くなり、実家は空き家に。
ですが、すぐに貸したり売ったりできるわけではありません。
なぜなら、実家の名義が親のままで、判断能力が低下していると、契約行為そのものができなくなるからです。
2 2025年問題とは何か?空き家と認知症の関係
2025年問題とは、1947~49年生まれの「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となり、社会保障や介護、住宅問題が一気に深刻化するとされる課題です。
住宅分野では、「実家を残したまま施設へ入る」→「実家は親名義のまま」→「認知症で契約も売却もできない」といった状況が、空き家増加の要因に。
名義人の意思能力がなければ、家の売却も賃貸もできません。
その結果、誰も住まないまま放置される「管理不能な空き家」が生まれるのです。
3 あなたの家庭は大丈夫?空き家予備軍チェック
こんなチェック項目に当てはまったら要注意です。
☑ 親が75歳以上で介護の話が出ている
☑ 実家は親名義のままで、相続登記は未了
☑ 自分は県外に家があり、戻る予定はない
☑ 親に認知症の兆しがある
☑ 家族で実家の今後について話し合っていない
一つでも当てはまれば、空き家になる可能性が高いと言えます。
4 親が施設に入り、実家が動かせなくなった60代男性のケース
鹿児島県の60代男性
母親が認知症と診断され、特別養護老人ホームに入所
実家は空き家となり、草木が伸び放題に。
「せめて貸して管理したい」と思ったものの、母の名義であり、本人の意思確認が取れず不動産契約ができませんでした。
選任された法定後見人は親族ではなく第三者の専門職後見人(弁護士)。
「事情を汲んでもらえるのか」「親の希望や家族の意向はどこまで反映されるのか」といった不安が先立ち、賃貸や売却の話は進まないままに。
結局、家は誰にも貸せずに、維持費や管理の手間だけが残ることに。
5 空き家にしないために、今できる3つの備え
①任意後見契約を活用する
元気なうちの親と契約を交わし、将来判断能力が落ちたときに備える制度です。
子供等が「後見人」として不動産契約や管理契約を代行できます。
・公正証書で作成(費用は5~10万円程度)
・親の意思能力があるうちにしか結べません
②家族会議をして方向性を決める
「実家をどうするか」「誰が管理するか」を家族で話し合うことも重要です。
親の希望を聞き、兄弟姉妹との連携を確認しておきましょう。
③相続登記の準備を進めておく
2024年から相続登記が義務化されました。
相続開始から3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料が発生することも。
実家の名義を早めに整理することが、空き家リスクの軽減につながります。
6 「契約」と「手続き」の壁を、行政書士がサポート
行政書士は、任意後見や相続、空き家管理などに関わる手続きをサポートします。
・任意後見契約の書類作成と公証役場との調整
・相続関係説明図や遺産分割協議書の作成
・空き家管理に関する委任契約や通知文の作成
・自治体からの「適正管理通知」への対応文作成
・不動産業者や造園業者との契約書作成や仲介支援
「何を、いつ、どこから始めればよいかわからない」
そんなときの伴走者として、行政書士は心強い存在です。
7 「親が元気なうち」が最大のチャンス
「空き家になったら考えよう」では遅いかもしれません。
親の介護や施設入所は、予想よりも突然やってきます。
そのとき、慌てず対応できるかどうかは、「今の準備」にかかっています。
任意後見契約、相続登記、家族会議--できることから始めてみませんか?
大切な実家を、未来につなぐために、今すぐ一歩を踏み出してみましょう。