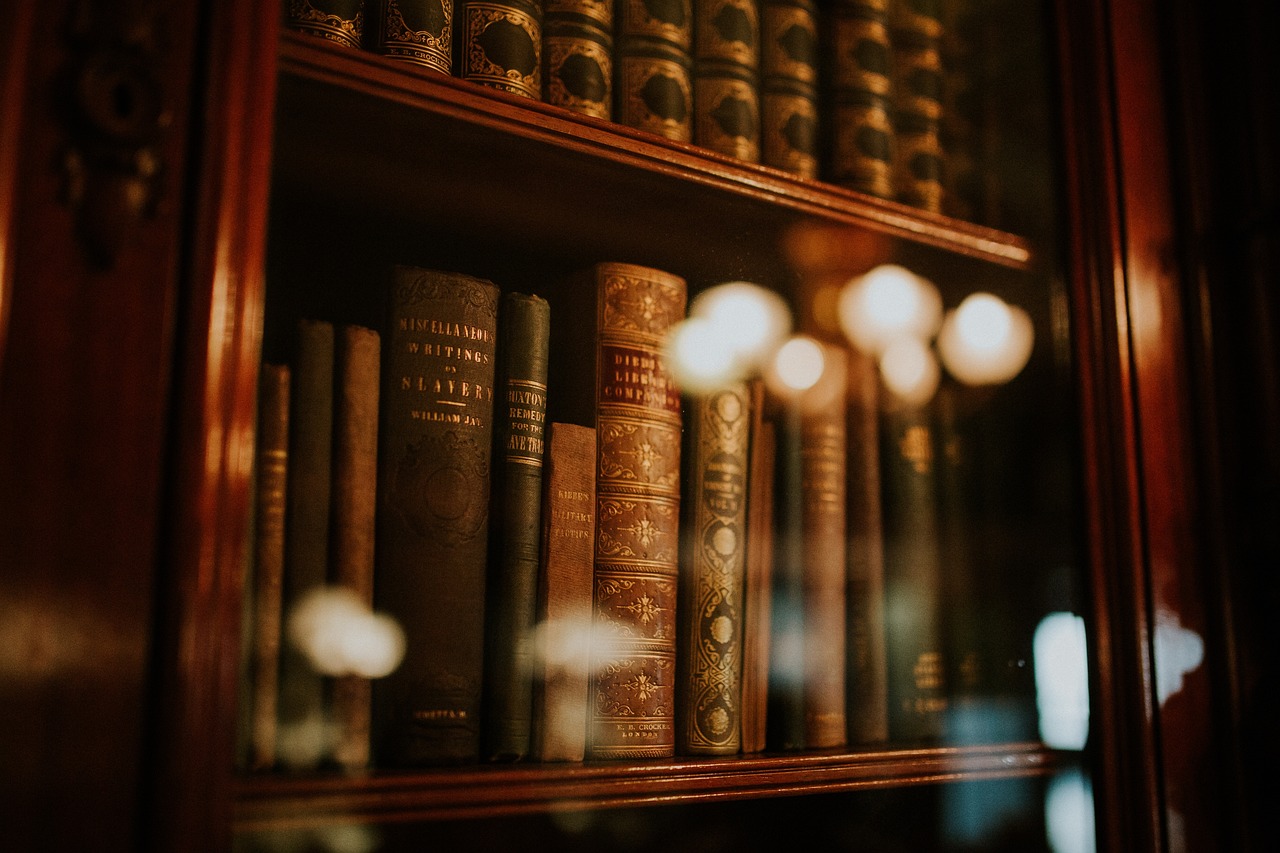「私たち夫婦、子どもはいないし…このまま何の準備もしなくて大丈夫かしら?」
60代、70代のご夫婦から、そんなご相談をいただくことが増えています。
年齢を重ねると、心配になってくるのが「お金」と「財産」の管理、そしてその行方。
とくにお子さんがいないご夫婦の場合、ご主人や奥様にもしものことがあった時、相続の手続きや生活費の管理が思わぬ負担になることも少なくありません。
今回は、老後やその後に備えて「今から知っておくべき3つの制度」について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1 「遺言」「後見制度」「家族信託」を理解しよう
お金や財産を守るために、ぜひ知っていただきたいのが次の3つの制度です。
①公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
②成年後見制度、任意後見制度
③家族信託(かぞくしんたく)
名前を聞いたことはあっても、「それってウチに必要なの?」と疑問に思われる方も多いはず。制度の違いや向き不向きを、身近なケースを交えながら見ていきましょう。
2 ①公正証書遺言 ― 自分の意思を「法的に残す」方法
【公正証書遺言とは?】
遺言には自分で書く「自筆証書遺言」もありますが、最も安全で確実なのが「公正証書遺言」。
これは、公証人(国が認めた法律専門職)に内容を伝え、公証役場で正式に作成される遺言書です。
【どんな人に向いている?】
・子どもがいない夫婦で、「すべての財産を配偶者に渡したい」人
・将来、兄弟姉妹が相続人となる場合に、トラブルを防ぎたい人
・確実に希望どおりの財産分けをしてほしい人
【身近な例】
例えば、夫が亡くなり、妻がすべてを引継ぐと思っていたら、兄弟にも相続権があることが判明。話し合いがまとまらず、相続手続きが何年も滞った…という事例も。
遺言があれば、こうしたトラブルを未然に防げます。
3 ②成年後見制度・任意後見制度 ― 判断能力が衰えたときの「代わりの手続き人」
【成年後見制度とは?】
高齢や病気によって、ご本人が判断できない状態になった時に、代わりに財産を管理・契約してくれる人(後見人)を選ぶ制度です。
・「法定後見」は、すでに認知症などが進行している場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
・「任意後見」は、元気なうちに「この人に任せたい」と契約で決めておける制度です。
【どんな人に向いている?】
・通帳や不動産の管理が自分でできなくなることが心配な方
・配偶者や信頼できる親族に任せたいが、正式な手続きが必要と感じている方
【注意点】
「後見制度を使えば安心」と思いがちですが、自由に財産を使えなくなることもあります。
特に法定後見は、家族でも不動産を売るのに裁判所の許可が必要になるなど、日常生活に影響が出るケースも。
だからこそ、元気なうちに「任意後見契約」を結ぶことがとても重要になります。
4 家族信託 ― 柔軟な財産管理ができる「新しい仕組み」
【家族信託とは?】
信頼できる家族に財産の管理、運用を任せる契約です。
例えば、「妻が認知症になったら、甥に不動産の管理を任せたい」といった希望を、契約によって実現できる制度です。
【どんな人に向いている?】
・高齢になったあとも、不動産や預貯金を柔軟に管理してもらいたい方
・後見制度では手続きが硬すぎる、という方
・子どもがいない夫婦で、親族にうまく役割分担をしてもらいたい方
【実際の活用例】
夫婦がそれぞれ信頼する甥や姪に財産の一部を管理してもらいながら、自分たちの生活費や介護費用に使ってもらう…そんなケースが増えています。
5 あなたに合った制度を早めに選ぶことが「安心」につながります
ここまで紹介した3つの制度は、それぞれ「財産を守る」「家族に迷惑をかけない」ため有効な手段です。
大切なのは、「元気なうちに考え始めること」。判断能力を失ってしまうと、できる選択肢がぐっと減ってしまうからです。
まずは、自分たちにとって何が必要かを整理し、できれば行政書士など専門家に一度相談してみてください。
「うちはまだ早いかな」と思っていても、実際に備えるタイミングは「今」が最適です。
些細なご相談からでも構いません。お気軽にご相談ください。
↓