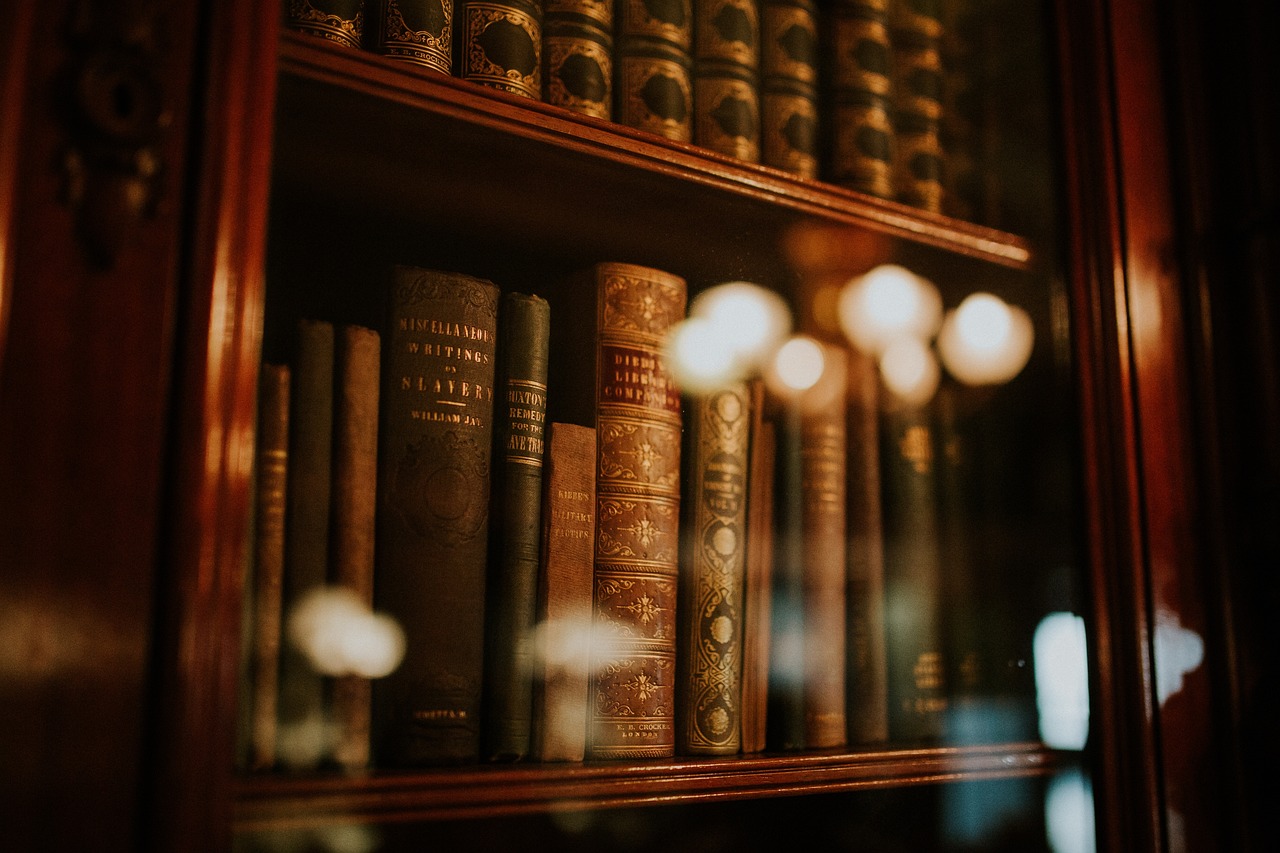「親が亡くなってすぐ、お金が必要になったのに通帳が使えない」
「口座はどうなる?凍結って何?誰がどう手続きするの?」
「兄弟が多くて話し合いも進まず、相続手続きが止まっている…」
親が亡くなった直後、身内の誰かがこうした不安に直面することは少なくありません。
突然の出費(葬儀、医療費、公共料金)も発生し、なおさら混乱しがちです。
この記事では、行政書士の立場から「通帳はなぜ凍結されるのか」「相続の手続きの流れ」「口座からお金を引き出す方法」について、最新の法改正を踏まえて分かりやすくご説明します。
1 通帳は、死亡が確認されると「凍結」されます
亡くなった親の通帳やキャッシュカードは、そのまま使えるわけではありません。
相続が発生すると、親名義の預貯金は相続財産として扱われ、銀行が「相続発生」を知った時点で口座が凍結されます。
具体的には、以下のようなきっかけで凍結されます。
・家族が銀行に「亡くなった」と伝えたとき
・相続人が残高照会などを問い合わせたとき
・金融機関が自治体などから死亡情報を把握したとき
一度凍結されると、キャッシュカードや通帳では一切の引き出しができなくなります。
2 原則「勝手に引き出すことはできない」が、一部は仮払い可能に
従来、遺産分割が終わるまでは、相続人であっても預金を1円も引き出すことができないというのが通例でした。
しかし、2019年7月1日に施行された民法改正(民法第909条の2)により、遺産分割前であっても一定額の仮払いが可能となりました。
この制度により、急ぎの出費(葬儀費用など)に対応しやすくなっています。
3 「仮払い制度」とは?
相続人が単独で預金の一部を引き出せる「仮払い制度」とは、次のような仕組みです。
・対象:被相続人の預貯金
・請求できる人:法定相続人(1人でもOK)
・金額:預金残高×1/3×法定相続分…条件①
※ただし、1金融機関あたり上限150万円…条件②
例えば、1,200万円の残高がある口座に対し、相続人が3人(配偶者、子2人)いる場合、
配偶者の仮払い金額は、
条件①:1,200万円×1/3×1/2(法定相続分)=200万円
条件②:150万円
→条件① > 条件②から、150万円を上限として引き出し可能です。
ただしこの制度は、「遺産分割が終わっていない段階での一時的措置」であり、払い戻した金額は、後の遺産分割で調整対象となります。
4 通帳を引継ぐには、遺産分割協議と書類の準備が必要です。
通帳(預金口座)を正式に相続するには、相続人全員で話し合って「誰が引継ぐか」を決める必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
そして、話し合いの内容を書面にまとめた「遺産分割協議書」を銀行に提出します。
併せて、以下の書類も必要になります。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍、住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・金融機関指定の相続届
特に被相続人の戸籍は、出生から死亡までの一式が必要で、複数の自治体にまたがっていたり、名前や本籍が変わっていると取得に時間がかかります。
こうした書類をすべて揃え、金融機関ごとに相続手続きを行います。
口座が複数ある場合、それぞれで同じ作業が必要です。
5 相続人が複数いる場合、合意がなければ手続きできません
通帳の相続人には「相続人全員の合意」が必要です。
誰か一人が勝手に手続きを進めることはできません。
例えば、長男が銀行に「父の口座は自分がもらいます」と申し出ても、他の兄弟の同意と印鑑証明がなければ受け付けてもらえません。
また、相続人の一部が協議に応じない、連絡が取れないといったケースでは、家庭裁判所に失踪宣告の申立てや不在者財産管理人の選任申立てが必要となることもあります。
6 行政書士に相談すれば、書類集めもスムーズに
戸籍の収集や財産の調査、協議書の作成は、想像以上に手間がかかります。
行政書士にご相談いただければ、
・戸籍謄本の収集(出生から死亡まで)
・財産目録の作成(不動産、預貯金など)
・遺産分割協議書の作成
・金融機関提出用の書類整備
など、相続に必要な事務的手続きスムーズに進められます。
「どこから手を付けたらいいか分からない」
「兄弟間の話し合いに不安がある」
「通帳や名義変更を間違いなく終わらせたい」
そうした方は、専門家に任せることで安心して進めることができます。
7 通帳は凍結される。でも対応策はあります
親が亡くなったあと、通帳は凍結され、勝手に使うことはできません。
しかし、2019年からの民法改正により、葬儀費用などに備えた「仮払い制度」も利用できるようになりました。
相続手続きには、書類の整備と相続人全員の合意が必要です。
話し合いがつかないまま放置すると、手続きができず、不動産や預金が「凍結されたまま」になってしまいます。
行政書士は、書類集めから協議書の作成まで、相続の土台を支えるパートナーです。
「これってどうすればいいの?」と思ったときには、どうぞお気軽にご相談ください。
↓